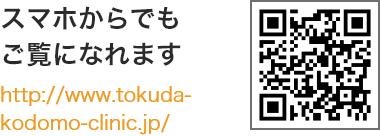- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- こどもの病気について
- 小児の発疹症について
こどもの病気について
小児の発疹症について
1溶連菌感染症(猩紅熱):A群溶連菌感染により発症します。莓のようにブツブツした舌、口囲蒼白、頚部リンパ節腫脹を認めます。発疹は、細かい紅斑様点状発疹で、次第に全身に拡がります。回復期には皮膚がはがれ落ちます(落屑)。合併症としては、中耳炎、肺炎、リウマチ熱、腎炎などがあります。
2 川崎病(MCLS):1967年に日本の小児科医が初めて報告した病気です。乳幼児、特に4歳くらいまでの子どもに起こりやすい病気で、全身の血管炎を引き起こす血管炎症候群です。未だに原因は不明ですが、下記のような症状が特徴です。
・高熱、両側の眼球結膜充血、
・真っ赤な唇とイチゴのようなブツブツの舌、
・体の発疹、手足の腫れや首のリンパ節の腫れ
・BCGの痕が紅くなる
などの症状があれば川崎病と診断します。
この病気で怖いことは『子どもでも心筋梗塞を引き起こす可能性がある』ことです。川崎病は全身の血管炎を引き起こす血管炎症候群であり、心臓の筋肉を養う『冠動脈』がコブのように膨らんで血液の通り道が狭くなっり、最悪の場合は血液の流れが止まってしまって、心筋梗塞を引き起こすことです。
このため、川崎病と診断されれば、小児の循環器専門医のいる施設での入院が必要となります。
3 伝染性単核症(EBウイルス感染症):発熱、リンパ節腫脹、咽頭発赤、発疹、肝脾腫大などの症状と、末梢血で異型リンパ球が出現します。本来、ウイルス感染であり対症療法でいいのですが、二次感染の予防のため、抗生物質が投与されることがあります。肝機能障害の出現に注意が必要です。
4 突発性発疹症:原因はヒトヘルペスウィルス6、7型です。生後6カ月~1歳頃にほとんどの子供がかかる病気で生まれて初めての発熱の場合が多い病気です。しかし、近年は3〜5歳頃でも罹患する人もあるようです。
高熱の割に全身状態は良好です。3日間程度、38~39℃の発熱が見られた後、解熱すると同時に全身に発疹が出現する病気です。熱性痙攣を起こすことがあり、注意が必要です。
5 伝染性紅斑(りんご病):
原因はパルボウイルス19です。りんご病とは、正式な病名は「伝染性紅斑」といい、潜伏期は約2週間。発疹のでる1週間位前が感染期間で、発疹出現後は感染させる危険がなくなりますので隔離する必要はありません。症状は頬がりんごの様に赤くなり、その後、腕や太ももに赤い斑点やまだら模様がでます。通常熱は出ないことが多く、出ても微熱程度です。発疹は1-2週間で自然に消えていきます。治療は特に必要ありませんが、かゆみが強いときはかゆみ止めを処方します。
6 薬疹(薬剤アレルギー):それまでの薬剤接種状況を詳しく調べます。
7 麻疹(はしか):原因は麻疹ウイルス感染ですが、ワクチンによる予防が可能です。
高熱とかぜ症状で始まり、2-4日後より発疹が出現します。発疹は紅色の丘疹で、上半身より 出現した後3日~4日で、解熱し快方に向かいます。4-5日過ぎても、高熱が持続したり呼吸困難、痙攣がある時は合併症が心配です。合併症には、中耳炎、肺炎、脳炎などがあります。
8 風疹(三日ばしか):原因は風疹ウイルスですが、ワクチンによる予防が可能です。
軽度の発熱と共に、まず顔面に発疹が現れ、耳の後ろや首筋のリンパ節が腫れることが多くみられます。3日間程度で解熱し発疹も消えます。合併症としては、関節炎、紫班病、脳炎などがあります。妊娠初期の妊婦との接触には注意が必要です。
9 水痘(みずぼうそう):
原因は水ぼうそう(水痘)ウイルスでが、ワクチンによる予防が可能です。
潜伏期間は約2週間で、軽度の発熱と同時に身体に発疹ができ、その中心部に水疱ができます。発疹・水泡は、頭の毛が生えている所、目の結膜、口の中にもできます。全ての発疹が乾燥し、かさぶた(痂皮化)になるまでは感染力があるので集団生活への参加(登園・登校)は不可。合併症には発疹からの細菌の2次感染、肺炎、脳炎、髄膜炎などがあります。
- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- こどもの病気について
- 小児の発疹症について
診療時間
- 診療時間
- 9:00-12:00
16:30-19:00
受付は診療終了の
30分前まで - 診療日
- 月・火・水・金
木・土の午前
第1・3の日曜午前 - 休診日
- 木・土の午後
第2・4・5日曜日
祝日 - 駐車場
- 8台
- お問い合わせ
- 06-6495-2772