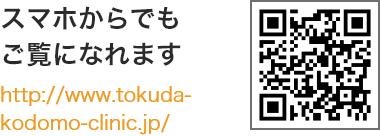- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- こどもの病気について
- マイコプラズマ肺炎
こどもの病気について
マイコプラズマ肺炎
肺炎の10~20%程度がマイコプラズマ肺炎といわれる程、よくある病原体です。5~14歳の年齢に多いのですが、成人や乳幼児にも感染します。肺炎と名付けられていますが『歩ける肺炎』と呼ばれるくらい全身状態が侵されない場合も多いようです。
マイコプラズマには通常処方されることの多いセフェム系抗生物質は無効で、マクロライド系抗生物質が有効ですが、マクロライド系抗生物質は子供には飲みにくいことが多いようです。このため、肺炎の原因がマイコプラズマか他の原因によるものかを確認することは、お子さんの治療を行う上で大事なことです。
【潜伏期】潜伏期は2~3週間程度といわれています。マイコプラズマ感染症の人と接触してもすぐに症状が出てくるのではなく、2~3週間の間をおいて症状が出現します。
【症状】発熱で発症し、1~2日遅れて咳が出現し、徐々に増えるというのが典型的な経過です。咳は最初は空咳ですがだんだん痰がからんできます。頭痛、全身倦怠感、咽頭痛を伴うことも多く、初期には上気道炎(いわゆる”かぜ”)と診断されることも多いです。
【どんな時にマイコプラズマ肺炎を疑うか】①家族内にマイコプラズマ感染症の人がいる場合
②保育園や幼稚園でマイコプラズマ感染症が流行している場合
③長期間せきが続く場合
④喘息児が気管支拡張薬などの治療にもかかわらず喘鳴が長引いたり、発作を繰り返す場合
⑤セフェム系抗生物質を使用しても発熱や咳嗽がなかなか治らない場合
【検査】発熱出現後5~7日程度経過すれば、マイコプラズマ感染症での検査が陽性になります。時には3~4日でわかることもあります。症状が出始めてからの期間が短いときは本当はマイコプラズマ感染なのに検査が陰性に出てしまうこともあります。
【合併症】喘息がある子供では喘息発作が生じたり悪化したりしますから注意が必要です。高熱のためにけいれんが誘発されたり、発疹が出現する、中耳炎を合併することもあります。
【治療】マクロライド系の抗生物質を出しますが味がよくないのが欠点です。薬剤はコーティングしていますが、コーティングがとれると薬の苦みが出ますから、手早く飲み込むのが薬を内服するこつです。アイスクリーム、コンデンスミルクやジャム、ケーキシロップなどに混ぜる方法がいいと思います。ただし、ヨーグルトに混ぜると苦みを生じますから避けましょう。
【登園・登校の目安】マイコプラズマ肺炎は学校保健安全法で「第三種学校伝染病」に指定されているため、急性期は出席停止となりますが、明確な出席停止期間は定められておらず、症状が軽快したら登園・登校が可能となります。
マイコプラズマ感染症が治るまでには、治療開始から早い場合で1週間程度を要します。
登園・登校については、出席停止期間の定めはありませんが、一般論として解熱剤を使用していない状態で24時間以内に37.5度以上の発熱がなく、食事がいつも通りに摂れ、さらに同居している人にとって、鼻水や咳が気にならないくらいまでが目安になると思います。
無理に登園・登校すると埃を吸ったり、走ったりした後で咳き込みがひどくなる可能性があると思います。
- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- こどもの病気について
- マイコプラズマ肺炎
診療時間
- 診療時間
- 9:00-12:00
16:30-19:00
受付は診療終了の
30分前まで - 診療日
- 月・火・水・金
木・土の午前
第1・3の日曜午前 - 休診日
- 木・土の午後
第2・4・5日曜日
祝日 - 駐車場
- 8台
- お問い合わせ
- 06-6495-2772