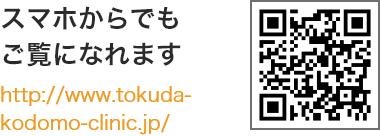- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- こどもの病気について
- 慢性甲状腺炎 (橋本病)
こどもの病気について
慢性甲状腺炎 (橋本病)
慢性甲状腺炎(橋本病)とは、甲状腺細胞に対する抗体(自己抗体)が産生されて甲状腺細胞が破壊されて甲状腺ホルモンが十分に作れなくなった状態で、甲状腺機能低下症とも呼ばれます。
甲状腺ホルモンは身体の新陳代謝に関係するホルモンであり、不足すると甲状腺が腫れて大きくなり、皮膚の乾燥、体重増加、顔面浮腫、無気力、行動力低下、体温の低下、便秘、過多月経、血中コレステロール値の増加等、代謝全般の不活発化がみられるようになります。甲状腺ホルモンの検査値が正常化したら、通常の生活が可能であり特に生活制限の必要はありません。
【原因】人間の身体の中には外敵から身体を守るために”免疫”という防御機能が存在しています。この防御機能の失調が原因と考えられています(自己免疫疾患)。このため、甲状腺細胞に対する自己抗体が産生され、甲状腺細胞が破壊されます。また、妊娠、出産、薬剤、感染等で非特異的な自己免疫反応の誘発が引き金となり、悪化するともいわれています。
【頻度】軽症、潜在性のものを含めると20-30代の女性の約25人に1人に存在するといわれています。家族内発生することもあり遺伝性もあると考えられています。
【症状】甲状腺の破壊が始まっても、残っている甲状腺細胞のホルモン分泌が十分であれば自覚症状はなく、甲状腺腫大のみの場合もあります。甲状腺の破壊が進むと甲状腺機能が低下し、ホルモンが十分作れなくなります。甲状腺ホルモンは身体の新陳代謝に関係するホルモンで、不足すると、皮膚の乾燥、体重増加、顔面浮腫、無気力、行動力低下、体温の低下、便秘、過多月経、コレステロールの増加等がみられます。 なお、甲状腺が破壊される時に甲状腺の中に蓄えられていた甲状腺ホルモンが血中に一気に漏出し、甲状腺機能亢進症と同じ症状(動悸、発汗過多等)が出現することがあります。このような例は通常、6カ月以内に自然に治癒しますが、その後逆に甲状腺ホルモンが不足するようになることがあります。通常、何度も繰り返すことが多い(再発、寛解を繰り返す)といわれ、定期的な血液検査が必要です。
【治療】甲状腺ホルモンが不足すれば、甲状腺ホルモン剤の投与が必要です。これは量さえ適当であれば、足りない分を補う補充療法であり、副作用は殆どありません。
※ 一時的な甲状腺ホルモンの過剰や不足の場合でも、その程度によっては、回復までの一時期に治療が必要になることがあります。
- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- こどもの病気について
- 慢性甲状腺炎 (橋本病)
診療時間
- 診療時間
- 9:00-12:00
16:30-19:00
受付は診療終了の
30分前まで - 診療日
- 月・火・水・金
木・土の午前
第1・3の日曜午前 - 休診日
- 木・土の午後
第2・4・5日曜日
祝日 - 駐車場
- 8台
- お問い合わせ
- 06-6495-2772