- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- メールマガジン
- 徳田こどもクリニック【メールマガジン3月13日分】
徳田こどもクリニック【メールマガジン3月13日分】
2008年3月13日
徳田こどもクリニック:3月16日(日)は診察しますが、20日(木)は休診です。インフルエンザは減りました。他には、嘔吐下痢症がありますが、全体的に多くはありません。子どもの気になる症状に『落ち着きがない』があります。最近は『注意欠陥多動性障害:ADHD』として、心配される方も少なくありません。しかし、乳幼児は好奇心に富み、行動するエネルギーにあふれています。好奇心が盛んで行動力にあふれるこの時期に、周囲のものや人に関心を示さない方がむしろ問題ではないかと思います。この時期の子どもは、自我に目覚め始めます。周囲の大人は衝動的にしかったりしないようにし、「がまん」と「待つ姿勢」を持つことが大切です。お誕生日を過ぎ、1歳半近くなるにつれ、子どもたちは「赤ちゃん」から「幼児」へと変わっていきます。このころによく聞かれるのが「落ち着きがない」とか「ちっともじっとしていることができない」という質問です。特に最近は「落ち着きのない子が増えている」とか注意欠陥多動性障害などといった行動発達に関する話題が新聞やテレビでもよく取り上げられており、心配されている方は少なくありません。 しかし、「落ち着き」とは何でしょうか? もともと乳幼児は好奇心に富み、行動するエネルギーにあふれています。ようやく一人で安定して歩けるようになり、興味や関心の赴くままに盛んに自分の周辺を探っている そんな子どもたちを大人の感覚で見れば、誰もが「落ち着きがない」と見えるのではないでしょうか。好奇心が盛んで行動力にあふれるこの時期に、周囲のものや人に関心を示さない方がむしろ問題ではないかと思います。 「落ち着きがない」と言われると、ついつい脳に何か問題があるのではないか、などと考えがちですが、心も急速に発達しつつある2 3歳児の行動異常を診断することはたやすくありません。やんちゃな子やわがままを通そうとしている子には時には厳しく対処し、また、優しく諭したりほめてあげましょう。この時期の子どもは、自我に目覚め始めます。周囲の大人は衝動的にしかったりしないようにし、「がまん」と「待つ姿勢」を持つことが大切です。
診療時間
- 診療時間
- 9:00-12:00
16:30-19:00
受付は診療終了の
30分前まで - 診療日
- 月・火・水・金
木・土の午前
第1・3の日曜午前 - 休診日
- 木・土の午後
第2・4・5日曜日
祝日 - 駐車場
- 8台
- お問い合わせ
- 06-6495-2772
アクセスマップ
当院へのアクセスはこちら
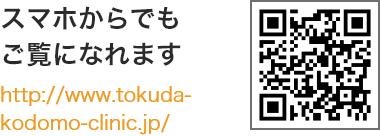
- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- メールマガジン
- 徳田こどもクリニック【メールマガジン3月13日分】
