- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- メールマガジン
- 徳田こどもクリニック【メールマガジン9月2日分】
徳田こどもクリニック【メールマガジン9月2日分】
2005年9月2日
子どもに多くみられ、卵や乳製品などを食べるとじんましんや呼吸困難を起こす「食物アレルギー」について、日本小児アレルギー学会(理事長・西間三馨国立病院機構福岡病院長)が初めて診療指針をまとめた。アレルギーかどうか分からないうちに、食品を控えさせる事例もあり、医療現場や家族の間で混乱が生じているためだ。また、妊娠後期や授乳期の母親が除去食を勧められるケースが多いが、「子どもへの予防効果はない」とした。 厚生労働省研究班の調査によると、食物アレルギーは、乳児が10%、3歳児が4~5%、学童期が2~3%の割合でいると推定されている。また、アレルギーがアトピー性皮膚炎を誘発するといわれているため、親が勝手に判断し食品を取ることを控えるケースも多いと専門家が指摘していた。 指針によると、アレルギーと診断するには、まず親が毎日何を食べて、どのような症状が何時間後に出たかを記した食物日誌をつけたうえで、医師が問診で原因を推定。あわせて血液などによる検査を行う。原因と推定された食品を含まない食事にして症状の改善を確認したあと、この食品を微量に含んだ食事(負荷試験)をして特定する。 負荷試験では、卵ならかたゆで卵の卵黄16分の1から、乳製品はヨーグルト(ミルク)4分の1さじから、小麦はうどん3~5センチ大1本から、それぞれ15~20分間隔で倍量にして症状を見る。 食物アレルギーは、年齢を重ねるごとに体内に耐性ができて食べられるようになる子が多い。そのため、アレルギーと判断されても、12~18カ月ごとに、チェックするよう目安を示した。 また、臍帯血(さいたいけつ)のなかの抗体を検査し発症を予知することは、「予知する感度が低く単独では勧められない」とした。 徳田こどもクリニック:9月11日(日)は休診です。日本小児アレルギー学会から食物アレルギーに関する診療指針が出ました。それによると、妊娠後期や授乳期の母親の除去食は、子どもへの予防効果はないとされています。また食物アレルギーの診断には、何を食べて、どんな症状が何時間後に出たかを記した食物日誌と医師の問診で原因を推定し、血液検査を行うこととなっています。不要な食物制限は、成長・発育を考えると避けるべきです。
診療時間
- 診療時間
- 9:00-12:00
16:30-19:00
受付は診療終了の
30分前まで - 診療日
- 月・火・水・金
木・土の午前
第1・3の日曜午前 - 休診日
- 木・土の午後
第2・4・5日曜日
祝日 - 駐車場
- 8台
- お問い合わせ
- 06-6495-2772
アクセスマップ
当院へのアクセスはこちら
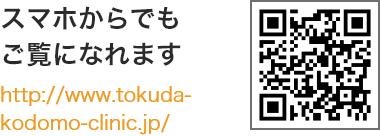
- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- メールマガジン
- 徳田こどもクリニック【メールマガジン9月2日分】
