- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- メールマガジン
- 徳田こどもクリニック【メールマガジン5月30日分】
徳田こどもクリニック【メールマガジン5月30日分】
2003年5月30日
最近の子どもは 「叱られる」ことを極端に嫌うようです。また、悪いことをしても、決して謝らない、なんだかんだと屁理屈で自分を正当化とする子が多いようです。子どもが悪いことをしたとき、親として注意したり、叱ったりすること当然ですが今の子どもたちには、それが素直に受け入れられず、かえって反感を買うような結果に終わってしまうことの方が多いようです。 それでは、どんな叱り方をすればよいのでしょう?子どもの叱り方で、まず言えることは、「叱り方」に公式はない ということですこういう「叱り方」をすれば子どもは必ずこうなる、ということは絶対にありません。100人の子どもには100通りの「叱り方」があるような気がするのです。そんなわけで、私が現職のときにやってきたことは、ひとりひとりの子どもの性格に応じた「叱り方」をしてきたつもりです。さらに、 「叱った」子どもに対して必ずその日のうちに「ほめる」場面をさがして、本気でほめてやる。ということも忘れないようにしてきたつもりです。 そうすることによって、いちど傷つけた子どもの「心の傷」を、できるだけ治してから帰宅させるように努めてきたつもりです。つぎに、叱るときは「本気で叱る」ことではないでしょうか。子どもは、親や先生の心の中を敏感に読み取ります。本気で叱ったときには、子どもの顔も変わります。時には、親や先生が涙を流しながら叱ることも必要なことだってあるのです。 さらに、子どもを「しかる」ときには、感情的に叱る親がいます。子どもが叱ってもなかなか言うことをきかないからといってヒステリックな叱り方をしているおかあさんをよく見かけますが、こういう叱り方は子どもにとって受け入れられないものです。あくまでも冷静にそして愛情をもって叱ってほしいものです。人は「叱られること」によって「悪」を知り、「ほめられる」ことによって「善」を知る、と言われます。どうか、子育て中のお父さんお母さん、上手な「叱り方」のできる親になって下さい。
診療時間
- 診療時間
- 9:00-12:00
16:30-19:00
受付は診療終了の
30分前まで - 診療日
- 月・火・水・金
木・土の午前
第1・3の日曜午前 - 休診日
- 木・土の午後
第2・4・5日曜日
祝日 - 駐車場
- 8台
- お問い合わせ
- 06-6495-2772
アクセスマップ
当院へのアクセスはこちら
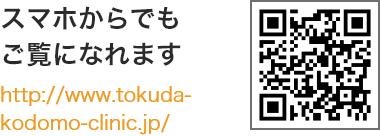
- 尼崎市の小児科【徳田こどもクリニック】トップページ
- メールマガジン
- 徳田こどもクリニック【メールマガジン5月30日分】
